Aug 03, 2025
【管理栄養士監修】オクラの健康効果を徹底解説!栄養を逃さない食べ方も紹介

独特のネバネバ食感が特徴のオクラ。夏野菜の代表格として知られ、手軽に調理できることから食卓にのぼる機会も多いのではないでしょうか。実はこのオクラ、私たちの健康維持に役立つ栄養素がたっぷり詰まった栄養満点の野菜なのです。
この記事では、たいや内科クリニックの管理栄養士・林安津美さん監修のもと、オクラに含まれる栄養素とその驚くべき健康効果について詳しく解説します。さらに、オクラの栄養を効率よく摂取するための調理法や、おいしいオクラの選び方、長持ちさせる保存方法まで、オクラを余すことなく楽しむための情報をお届けします。
MOKUJI
オクラに含まれる栄養素は?
オクラには、私たちの体に必要な様々な栄養素がバランス良く含まれています。特に注目したいのは、ビタミン、ミネラル、そして特徴的なネバネバの元となる食物繊維です。これらの栄養素が、私たちの健康を多方面からサポートしてくれます。
ビタミン

オクラには、体の調子を整えるために欠かせないビタミン類が豊富です。
【βカロテン(ビタミンA)】
βカロテンは、体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。ビタミンAは、目や皮膚、粘膜の健康を維持し、免疫機能を正常に保つ働きがあります。また、強力な抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐ効果も期待できます。油と一緒に摂取することで吸収率が高まる脂溶性ビタミンです。
【ビタミンC】
ビタミンCは、コラーゲンの生成を助け、皮膚や血管を丈夫に保つ働きがあります。また、抗酸化作用により、免疫力を高めたり、ストレスへの抵抗力を強めたりする効果も期待できます。
【ビタミンK】
ビタミンKは、血液の凝固に関わる重要なビタミンです。 また、骨の健康維持にも不可欠で、カルシウムが骨に沈着するのを助ける働きがあります。
【葉酸】
葉酸は、ビタミンB群の一種で、赤血球の生成を助けることから「造血のビタミン」とも呼ばれています。 細胞の分裂や成長にも深く関わっており、特に妊娠初期の女性には重要な栄養素です。
【ビタミンB1、B2、ナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸】
これらのビタミンB群は、主にエネルギー代謝を助ける補酵素として働きます。 糖質や脂質、たんぱく質からエネルギーを作り出す際に不可欠な栄養素です。
ミネラル類

オクラには、体の機能を維持・調節するミネラル類も含まれています。
【カリウム】
カリウムは、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、血圧を正常に保つ働きがあります。 また、筋肉の収縮や神経伝達にも関わっています。
【カルシウム】
カルシウムは、骨や歯を形成する主要なミネラルです。不足すると骨粗しょう症のリスクが高まります。 また、筋肉の収縮や神経の興奮を抑える働きもあります。
【マグネシウム】
マグネシウムは、カルシウムとともに骨の健康を支えるほか、体内で300種類以上の酵素の働きを助ける重要なミネラルです。エネルギー産生や筋肉の収縮、神経伝達などに関わっています。
食物繊維

オクラの最大の特徴ともいえるネバネバの正体は、主に「水溶性食物繊維」のペクチンよるものです。さらにオクラには「不溶性食物繊維」もバランスよく含まれており、この2種類の食物繊維が健康に良い影響を与えます。
【ペクチン(水溶性食物繊維)】
糖質の吸収を穏やかにし、食後の血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。 また、コレステロールの吸収を抑制し、血中コレステロール値を下げる効果も期待できます。腸内では善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに役立ちます。
【不溶性食物繊維】
便のカサを増やし、腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にすることで、便通を促し便秘解消に貢献します。
オクラで得られる代表的な健康効果

オクラに含まれる豊富な栄養素は、私たちの体に様々な喜ばしい効果をもたらしてくれます。 代表的な健康効果を見ていきましょう。
整腸作用と便秘解消
オクラのネバネバ成分であるペクチンなどの水溶性食物繊維は、腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えます。 また、便を柔らかくして排出しやすくする効果もあります。
一方、不溶性食物繊維は便のカサを増やして腸を刺激し、排便を促します。この2つの食物繊維の相乗効果により、腸内環境が整い、便通のリズムを正常に保つ効果が期待できます。
美肌や免疫力アップ
オクラに含まれるβカロテンは、体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあります。これにより、肌荒れを防ぎ、健やかな肌を保つ美肌効果が期待できます。
また、βカロテンやビタミンCには抗酸化作用があり、免疫細胞を活性化させることで免疫力を高め、風邪や感染症にかかりにくい体づくりをサポートします。 【管理栄養士監修】美肌に効果的な食事って?必要な栄養素と食生活を徹底解説
【管理栄養士監修】美肌に効果的な食事って?必要な栄養素と食生活を徹底解説
血糖値コントロールや生活習慣病予防
オクラの水溶性食物繊維であるペクチンは、糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。これは、糖尿病の予防やコントロールに役立ちます。 また、コレステロールの吸収を抑える働きもあるため、血中コレステロール値の改善や動脈硬化の予防にも繋がり、生活習慣病のリスクを低減する効果が期待できます。
ダイエットにもおすすめ
オクラは100gあたり約26kcalと低カロリーな野菜です(文部科学省 食品成分データベース)。食物繊維が豊富に含まれているため、少量でも満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。
また、血糖値の急上昇を防ぐことは、インスリンの過剰分泌を抑えることに繋がるため、結果として脂肪の蓄積を抑える効果が期待されます。そのため、オクラはダイエットを意識した食事にも適しています。 【管理栄養士監修】ダイエット中に食べてもいいおやつって?太りにくい間食を選ぶポイントを解説!
【管理栄養士監修】ダイエット中に食べてもいいおやつって?太りにくい間食を選ぶポイントを解説!
オクラの栄養は調理で変わる?
オクラの栄養を効率よく摂るためには、調理方法も大切です。調理法によって栄養価にどのような違いが出るのか見ていきましょう。
オクラは生と茹でたもので栄養に違いはある?

オクラに含まれるビタミンCや一部のビタミンB群などの水溶性の栄養素は、茹でることでお湯に溶け出してしまう可能性があります。そのため、これらの栄養素を効率よく摂りたい場合は、生で食べるか、茹で時間を短くするのがおすすめです。また、栄養保持には水を使わない調理法も役立つため、蒸す・電子レンジで加熱するといった方法も取り入れてみましょう。
ただし、加熱することでカサが減り、たくさん食べやすくなるというメリットもあります。生のオクラと茹でたオクラの栄養価を比較すると、一部の水溶性ビタミンは茹でることで減少するものの、その他の主要な栄養素に大きな変動はないとされています。
冷凍すると栄養価は変わる?

オクラを冷凍しても、栄養価が大きく損なわれることはありません。 むしろ、旬の時期に収穫された栄養価の高いオクラを冷凍保存することで、手軽に栄養を摂取できます。正しく下処理をして冷凍すれば、食感や風味も比較的保たれます。
ただし、自宅で冷凍したオクラと市販の冷凍オクラでは、衛生面や冷凍技術に差があります。とくに自宅では急速冷凍が難しいため、食感や品質の劣化が早まりやすい点に注意が必要です。自宅で冷凍した場合は、なるべく早めに使い切るようにしましょう。
加熱すると栄養価は変わる?
ビタミンCなどの水溶性ビタミンは加熱によって一部失われる可能性があります。 しかし、βカロテンのような脂溶性ビタミンは、油と一緒に加熱調理することで吸収率が高まります。 そのため、調理方法によって得られる栄養のメリットが異なると言えるでしょう。
栄養を逃さないためのオクラの調理法

オクラの栄養をできるだけ逃さずに摂取するためには、いくつかのポイントがあります。
【茹でる場合は短時間で】
水溶性ビタミンの流出を最小限に抑えるため、茹で時間は短くしましょう。沸騰したお湯で30秒~1分程度が目安です。
【電子レンジ加熱もおすすめ】
水を使わない電子レンジでの加熱は、水溶性栄養素の損失を抑えるのに効果的です。
【汁ごと食べられる調理法を選ぶ】
スープや味噌汁など、溶け出した栄養素も丸ごと摂取できる調理法もおすすめです。
【板ずりをする】
オクラの表面にあるうぶ毛は、塩をまぶしてまな板の上で軽く転がす「板ずり」をすることで取り除くことができます。口当たりが良くなるほか、色もきれいに仕上がります。
相乗効果で栄養抜群!おすすめの食べ合わせ
オクラは他の食材と組み合わせることで、さらに栄養効果を高めることができます。
油と一緒に

βカロテンは脂溶性ビタミンなので、油と一緒に調理することで吸収率がアップします。炒め物や和え物に少量の油を使ったり、オイル系のドレッシングをかけたりするのがおすすめです。
豚肉・納豆など

【豚肉】
豚肉には、オクラには少ないたんぱく質や、糖質の代謝を助けるビタミンB1が豊富に含まれています。 一緒に摂ることで、疲労回復効果や体力アップが期待できます。
【納豆】
納豆に含まれるナットウキナーゼには血栓を溶かす働きがあるとされており、オクラのβカロテンが持つ抗酸化作用と合わせることで、動脈硬化の予防効果がさらに高まると期待されています。また、どちらもネバネバ食材なので、食感の相性も抜群です。
他のネバネバ食材と合わせて

山芋やモロヘイヤ、なめこなど、他のネバネバ食材と組み合わせるのもおすすめです。 さまざまな種類の食物繊維を一緒に摂ることで、整腸作用や消化促進の相乗効果が期待できます。
おいしいオクラの選び方

せっかく食べるなら、新鮮でおいしいオクラを選びたいですよね。以下のポイントをチェックしてみましょう。
【うぶ毛がびっしり】
新鮮なオクラは、表面全体に細かいうぶ毛がびっしりと生えています。触るとチクチクするほどしっかりしているものが新鮮な証拠です。
【鮮やかな緑色】
色が濃く、鮮やかな緑色をしているものを選びましょう。黒ずんでいたり、色が薄くなっていたりするものは鮮度が落ちている可能性があります。
【ハリと弾力がある】
触ってみて、ハリと弾力があるものが新鮮です。しなびていたり、柔らかすぎたりするものは避けましょう。
【ヘタや切り口が変色していない】
ヘタやガク、切り口が黒っぽく変色していないものが新鮮です。
【大きすぎないもの】
一般的に、大きすぎるオクラは育ちすぎて筋っぽく、味が落ちていることがあります。小ぶりなものの方が柔らかく、味が濃い傾向にあります。五角形や六角形の角がはっきりしているものが良いでしょう。
長持ちさせたい!オクラの正しい保存方法

オクラは比較的傷みやすい野菜なので、正しい方法で保存することが大切です。
オクラは低温と乾燥に弱いため、キッチンペーパーや新聞紙で包んでからポリ袋に入れ、ヘタを下にして野菜室で立てて保存するのがおすすめ。 この方法で4~5日程度保存可能です。
また長期間保存したい場合は、冷凍保存が便利です。
【生のまま冷凍】
板ずりをしてうぶ毛を取り、ヘタとガクを処理した後、水気をしっかり拭き取ってから冷凍用保存袋に入れて冷凍。
【茹でてから冷凍】
板ずりをして硬めに茹で(15秒~30秒程度)、冷水で冷やしてから水気をしっかり拭き取り、使いやすい大きさに切るか丸ごと冷凍用保存袋に入れて冷凍。
食べたいときにいつでも使えるので、たくさん手に入ったときは冷凍しておくといいですね。冷凍保存の場合、約1ヶ月程度保存可能です。 冷凍ストックでごはん作りが変わる!食材別の保存術まとめ
冷凍ストックでごはん作りが変わる!食材別の保存術まとめ
まとめ

オクラは、食物繊維をはじめ、βカロテン、ビタミンC、カリウムなど、私たちの健康と美容に嬉しい栄養素が豊富に含まれる緑黄色野菜です。その健康効果は、整腸作用による便秘解消から、血糖値コントロール、免疫力アップ、生活習慣病予防、さらにはダイエットサポートまで多岐にわたります。
調理法を工夫したり、相性の良い食材と組み合わせたりすることで、オクラの栄養をより効果的に摂取することができます。選び方や保存方法のポイントを押さえて、栄養満点でおいしいオクラを日々の食事に取り入れ、健康的な毎日を送りましょう。 夏野菜の漬物で夏バテ防止!食欲がないときでも食べられるおすすめ簡単レシピ
夏野菜の漬物で夏バテ防止!食欲がないときでも食べられるおすすめ簡単レシピ
【お詫びと訂正】
「オクラに含まれる栄養素は?」の記事内、食物繊維の項目にて、オクラのねばねばの正体を「糖たんぱく質のムチンなどによるもの」と記載しておりました。
しかし、オクラにはムチンは含まれておらず、また植物全般にムチンは存在しません。
誤った記述がございましたことを、ここに訂正しお詫び申し上げます。

林 安津美
管理栄養士/病態栄養専門管理栄養士/日本糖尿病療養指導士/腎臓病療養指導士/がん病態栄養専門管理栄養士/和漢薬膳師等
あいち厚生連で37年間病院の管理栄養士として勤務。その間豊田厚生病院・安城更生病院の技師長として17年間在籍。2022年5月よりたいや内科クリニックへ入職。患者さんの思いを聴き・応え、患者目線でテーラーメイドの医療をお届けできるよう努めている。
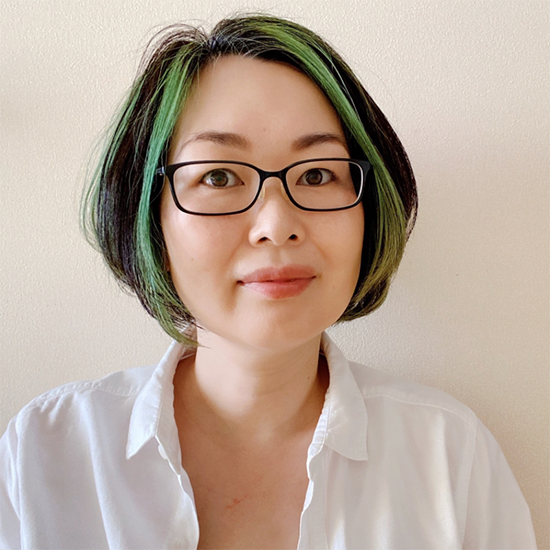

「伝わる」「感じる」文章をお届けするフリーランスライター。美容や健康に気を使いたいお年頃。美味しいものとNetflixが大好きなインドア派ママです。






